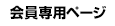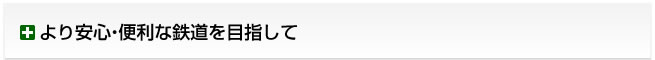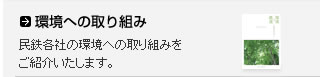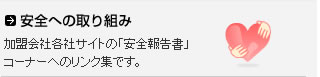鉄道Q&A
- 防災・減災のための取り組みって、どんな取り組みですか?
大規模な自然災害を想定して、ハード・ソフトの両面から乗客の安全確保のための対策が講じられています。
[解説]
近年、わが国では大規模な地震、台風、集中豪雨などの自然災害が多発し、鉄道にも大きな被害をもたらしています。民営鉄道各社は、かねてより災害時における乗客の安全確保や迅速な現場復旧のための対策を講じてきましたが、新たに防災・減災の見地からこれまでの取り組みを一層強化するとともに、「災害に強い鉄道」を目指し、残された課題や新たな課題の解決にも積極的に取り組んでいます。
地震対策としては、①駅・鉄道施設の計画的な「耐震補強工事」の実施、②緊急地震速報を受けたときに列車を緊急停止させる「早期地震警報システム」の導入、③地震計と連動した運転規制、などがあげられます。また、台風・豪雨などの自然災害対策としては、①詳細な気象情報の入手など監視体制の強化、②雨量情報と連動した運転規制、③「計画運休」に向けた社内体制の整備、などがあげられます。さらに、地震などにより鉄道が運休したときの帰宅困難者対策や、外国人旅行者に対する適切な情報提供なども、国のガイドラインに沿ってマニュアルが作成されています。
なお、地上も地下もコンクリートの建造物や構造物で覆われた大都市圏では、台風などで集中豪雨となると、雨水が地下鉄や地下街に流入するおそれがあります。こうした災害を防ぐため、地下鉄では浸水の危険のある換気口に、電動式浸水防止機を設けたり、トンネルの出入口にも浸水防止策を講じたりしています。万一浸水した場合には、防水ゲートでトンネルを全面的に閉鎖し、鉄道施設を水害から守る対策も用意されています。(→鉄道用語事典「鉄道気象通報」、「計画運休」)


その他鉄道Q&A
- 公共交通機関の基本原則である「安全」を確保するため、民営鉄道はどんな努力をしていますか?
- 台風や地震などが発生した場合、列車の安全運行はどのようにして保たれているのですか?
- 防災・減災のための取り組みって、どんな取り組みですか?
- 不測の事態に備えて行われる「異常時の総合訓練」って何ですか?
- 運転士になるためにはどんな訓練が必要ですか?
- 電車が、他社路線に入るときに、運転士は交代するのですか?
- 踏切事故などにより列車ダイヤが乱れたときは、どのようにして正常ダイヤに戻しているのですか?
- 鉄道の「上り」「下り」って何ですか?
- 電車は、踏切や駅を通過する際、警笛を鳴らすときがありますが、この警笛はいつ、どのような目的で鳴らすのですか?
- 民営鉄道のレールの幅は、どの鉄道会社も同じなのですか?
- ひとつの電車を作るのにどのくらい期間がかかるのですか?
- 駅の構内で迷わないようにするため、どんな案内システムが導入されていますか?
- 近年、駅や電車内の快適性が高まっているといわれますが、どんな取り組みが進められているのですか?
- 民営鉄道は、沿線住民とのコミュニケーションを図るため、どんな活動をしていますか?
- 最も古い民営鉄道って、どこの会社ですか?また、初めての路線はどこですか?
- 鉄道は、自家用車や飛行機などの交通機関と比べて環境にやさしいと言われますが、本当ですか?